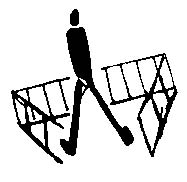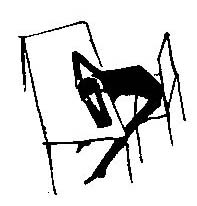境界線のF.カフカ
salon de“kafka”

| F.カフカ(1883〜1924)は死に際し友人に自筆の書の一切を焼き捨てるように頼んだといいます。 しかしながら、友人の誠実なる裏切りによって、その言葉は残されました。 さて、 『海辺のカフカ』 に散りばめられた言葉やその行間に流れる作者の思考に思いをめぐらす時、 遺されたF.カフカの言葉は長い時を超えて共鳴してくるようです。 ここではそうした言葉を中心に私の心を揺り動かすカフカの言葉をご紹介させていただきます。 |
|
|
||||||||||||
|

| 境界線のF.カフカ 労働災害保険協会に公務員として勤めながら作品を書き続け、公務員と作家という二足のわらじをはいたユダヤのカフカ。官僚機構の末端にあって、世紀末の憂鬱と現実の甘美なる虚構性をその冷たい眼差しで見つめていたのだろう。時代はそしてプラハは近代の思想と文化の隆盛そして退廃という二重性を孕んでいた。ヤノーホの父によればカフカは友達づき合いするには、あまりに控え目で、あまりに自分を閉ざしていたといいます。その目はカラスを自分の中に棲まわせて、世界を俯瞰していたのだろうか? カフカは 厳格なる言葉でありながら曖昧性を表出し、境界を超えあるいは境界の消えた世界を呈示する。 私とは、存在するとはそこに在ることだけでなく同時にそこに属することを意味するという。 性急な解釈を退け、想像力を喚起させる言葉 善なるものの偽善性と悪との表裏を警告する 君と世界の戦いでは世界の側に立てと云う 主知的なる葛藤を通じながらそれを拒否するカラスの眼差し そして 生の可能性と最期の一息に得られるやもしれない最初にして最後の展望へと・・・ |
| 村上春樹は『海辺のカフカ』を通じF.カフカそのものに近接し、今、現在を生きる私たちに、様々なる想像力を喚起させようとしているのだろうか? |
writing & photos
NASCI/021019
境界線のカフカ
| * | 挿絵は『夢・アフォリズム・詩』及び『カフカのかなたへ』池内紀、講談社学術文庫1998より F.カフカ自筆イラスト、写真は『変身』カフカ、新潮文庫、表紙より加工したものです |
| [言の葉 拾い] [海辺のカフカ 詩めぐり] [不思議カフカ] [境界茶論] [salon de“kafka”bbs] |
![]()
Copyright(C)2002-
NASCI All rights reserved.