対立と両義性の中で
salon de“kafka”
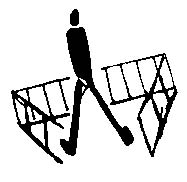
以下の文章はもえぎさんによる掲示板への書き込みに始まるログの掲載です
| 物語がもたらすもの 2002/11/01 12:00 From:もえぎ |
||
|
№28 境界線を引くということ より つまり認識とは境界を明確にする行為であり、 関係における差別化、差異化によって そのもの自体をはじめて理解することができると考える * * * * * * 近代知以前 人は単純化された世界(神話と宗教)のなかで ある意味ではみな わかりやすい闇 を持っていた。 しかし われ想うゆえにわれあり 近代知を得ることで 自分でも理解しがたい重い闇を引きずらざるをえなくなった。 NASCIさんのことば >・・・関係における・・・ に非常に興味深いものを感じました。 世界を測るものさしをもつこと。それは一人一人ひとつひとつみな違う。それは関係性という場に出ていってこそはじめて理解でき、確かな効力を持つ。違うからこそ・・・ カフカくんが母なるものの闇を許し超え 東京という混沌の関係性の中に挑んでゆく姿は、やはり すべてはこれからだ という あたたかい力を感じました。 |
||
| 世界を測るものさし 2002/11/05 21:57 From:NASCI もえぎさん書き込みありがとう そういえば『風の歌を聴け』の中で 「ものさし」についての印象的な文章がありましたね 少し紐解いて手繰り寄せてみました |
||
|
||
| 僕はノートのまん中に1本の線を引くようなこともしたことないけれど・・・ もえぎさんの云うように 一人一人ひとつひとつみな違うものさしを持っているわけで 「僕」や「私」から見た「ものさし」は、 関係性という場に出ていってこそはじめて理解でき、確かな効力を持つのでしょうし、 それはそれでも他者にとっては闇でもあるのでしょう。 だからこそ関係性を閉ざすのではなく外へと開き 関係性を意識して「ものさし」を示しあう可能性がまだまだ開けている カフカくんには応援したいとする作者の熱い眼差しを感じられるようです。 |
||
| 対立と両義性の中で 2002/11/08 22:58 From:NASCI もえぎさんの「ものさし」から『風の歌を聴け』を振り返ってみましたが その中で、「鼠」と「僕」の交わした何気ない会話に、 その後の「僕」そして村上春樹氏自身の物語や世界を構築していく上で 基底となり「配電盤」のごとく横たわり続けることになる思考を 読み取ることのできる文章に出会いました。 * * * 「『優れた知性とは二つの対立した概念を同時に抱きながら、その機能を充分に発揮して いくことができる、そういったものである。』」(鼠) 「誰だい、それは?」(僕) 「忘れたね。本当だと思う?」(鼠) 「嘘だ。」(僕) 「何故?」(鼠) 「夜中の3時に目が覚めて、腹ペコだとする。冷蔵庫を開けても何も無い。 どうすればいい?」(僕) 鼠はしばらく考えてから大声で笑った (以上(『風の歌を聴け』16章より) * * * その後この会話に対しては、ここで笑い飛ばされているように それ以上触れられることはなかったのですが 注意して読むと、境界線をめぐる思考を そして世界を測るものさしへと つまり「僕」の、世界との関係における身の振り方へ 目が向けられていたのだと、理解することができるようです。 直接的には、「二つの対立した概念を抱きながら、その機能を発揮していくことができる」 知性なんて「僕」には持ち得ないし、もしくはそんな知性なら糞食らえとでも 「僕」は言いたかったのでしょう。 そして「鼠」の笑いは、 「鼠」自身二つの対立した概念を同時に持ち合わせる つまり折り合いをつけてうまくやっていくことの意味を 深く考えようとしていたのでしょうし、 それを腹ペコと空の冷蔵庫の喩えで即座に否定してしまう 「僕」の明快さに、そんなことで悩む自分がなんともバカバカしく、 胸のすくような思いがしたから、しばらく考えてから大声で笑ったのだと 解することができるように思われます。 つまり「僕」の喩えの明快さと「鼠」自身に対して笑ったと。 ところで、この「僕」の喩えは 1章の最後に出てきます 「夜中の3時に寝静まった台所の冷蔵庫を漁るような人間には、 それだけの文章しか書くことはできない。 そして、それが僕だ。」 そしてその前にある言葉として、つまり先に引用した 「 ~ まん中に線が1本だけ引かれた一冊のただのノートだ。」 に続いて以下の文章があります。 「教訓なら少しはあるかもしれない。 もしあなたが芸術や文学を求めているのならギリシャ人の書いたものを読めばいい。 真の芸術が生み出されるためには奴隷制度が不可欠だからだ。古代ギリシャ人がそうであったように、奴隷が畑を耕し、食事を作り、船を漕ぎ、そしてその間に市民は地中海の太陽の下で詩作に耽り、数学に取り組む。芸術とはそういったものだ。」 この時「僕」はきっと紛れもなくこちら側の人間であるということを 自覚していたのでしょう。 そしてロマンを語りたいなら古代ギリシャ人を見習うがよいと。 それはある種の諦めと冷めた感情の表明であり リアリズムの中に自らを位置づけていたと考えられます。 芸術や文学を現実の向こう側へと追いやり、 それを語ることの欺瞞性を摘発しているようにも感じられます。 そしてそれは両義的であることの困難さから逃れているようでもありました。 しかし、その後続く物語りにおける「僕」は、 いつもその両義性の中で境界をさまよい続けることになります。 こうして村上春樹氏のデビュー作『風の歌を聴け』を今少し振り返ってきましたが、 そこで発せられた言葉は、確実に『海辺のカフカ』へと受け継がれ、 語る存在としての大島さんやカラスと呼ばれる少年の言葉に重なり合いながら カフカくんの態度へと繋がっているようです。 「境界」をさまよい、ぎりぎりまで見つめておきながら 結局のところ向こう側に行ってしまうことなく、 こちら側の世界を受け入れるということに。 |
writing & photos
NASCI/021119
境界線のカフカ
![]()
Copyright(C)2002-
NASCI All rights reserved.